創設者、大滝政治の想い

戦前の砂町保育園
関東大震災からの復興の中で、子どもたちへの保育を始める
社会福祉法人東京児童協会創設者大滝政治は1905年(明治38年)、新潟県直江津(現在の上越市)に生まれました。大滝政治は、幼少の頃、寺の日曜学校で学んだ精神や生き方を子どもたちに伝えることを自らの使命として、子どもたちが集い学ぶ保育園づくりに一生を捧げた人でした。
大滝政治が上京した頃の東京は、関東大震災による建物の倒壊や焼失で混乱の最中でした。地区の大半が甚大な被害を受けた猿江地区(江東区)でも、住む家を失った多くの人々が焼け跡での仮設暮らしを強いられていました。
そんな中、日々の生活と復興に必死の大人たちの傍らで、放ったらかしにされてしまっている子どもたちを救おうと立ち上がった有志の一人が大滝政治でした。そして、バラックが立ち並ぶ仮設地区(現在の猿江恩賜公園)の一角で、子どもたちの青空保育をスタートしたのです。

船堀保育園(現船堀中央保育園)
生き生きと遊ぶ子どもたちの姿が周囲の方たちを動かし、
保育事業がスタート
大滝政治らは、それぞれの得意分野を活かして集まった子どもたちに詩や歌・踊りやお遊戯を教えました。 夜間は警備員などの仕事に就き、一日中働きながら子どもたちのために心血を注ぐ政治らの献身的な姿はやがて、周囲の大人たちの心を動かしました。
生き生きと遊ぶ子どもたちの笑顔を見た地域の人々の間で「この地にこの子たちのための幼稚園をつくろう」という機運が高まり、昭和5年の大島中央幼稚園の設立につながりました。つづく昭和9年には現在の砂町保育園の前身である砂町幼稚園、昭和15年には船堀中央保育園の前身である船堀保育園を設立。
こうして各地での保育事業がスタートした背景には、大滝政治らの涙ぐましい努力のうえに、それぞれの地域の方々の厚意と協力があったことは言うまでもありません。

昭和34年 船堀保育園・大滝学園
さまざまな支えによって戦災を越え、戦後へ
その後、第二次世界大戦の開戦に伴い戦時体制下に入り、戦局の悪化により戦時託児所となった各園でしたが、軍需工場への接収の危機や昭和20年3月の東京大空襲による園舎焼失等を乗り越え、終戦後も保育事業を継続できたのはやはり、妻・君子(のちの二代目理事長)や家族に加え、長い歳月の中で培われた幾多の人たちの暖かい支えがあってこそでした。
幸いにも戦災を免れた船堀保育園(現:船堀中央保育園)の園舎の半分を移築し、同年12月には砂町での保育を再開した大滝政治の行動力も、そうした沢山の思いに支えられたものでした。
社会福祉法人として新たな歴史を。そして、現在まで受け継がれる思い
昭和35年に社会福祉法人として認可を受け、大滝政治を初代理事長として新しい児童福祉の歴史を歩みはじめた東京児童協会は、2代目理事長・大滝君子、3代目・重野新子、4代目・大滝政昭、5代目・大滝貞代と、その後も地域のニーズや支援を受けながら、変わらない思いで保育事業を展開してきました。
創設者の思いを受け継ぎ、これからも子どもたちのよりよい未来のため、地域の人々と手を携えて保育の歴史の新しい1ページを築いていきたい。それが今も昔も変わらない私たちの願いです。
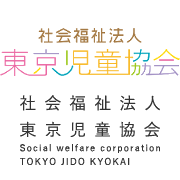

















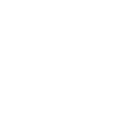
 東京児童協会のご案内
東京児童協会のご案内 ↑ページトップへ戻る
↑ページトップへ戻る